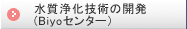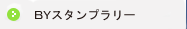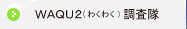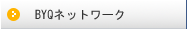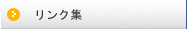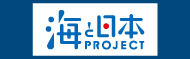| TOP>琵琶湖・淀川流域の水環境情報>琵琶湖・淀川流域の水環境の現状(琵琶湖の水質) |
| ●琵琶湖の水質 |
|
【透明度】
|
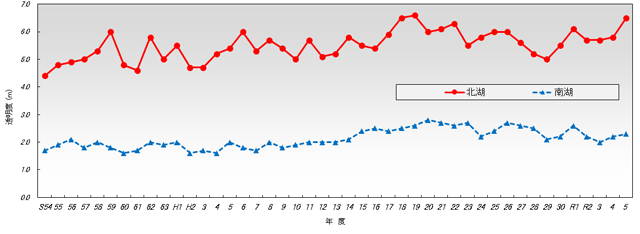 |
|||
| 琵琶湖の透明度(年平均値)の推移 | |||
滋賀県「環境白書」より作成
|
|
【CODおよびBODの年平均値の推移】
|
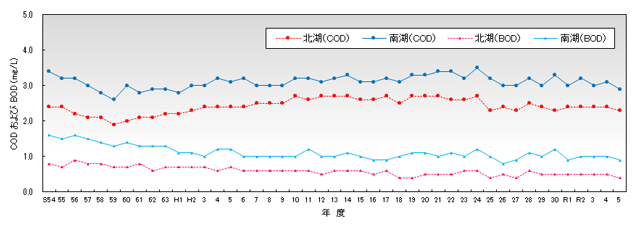 |
|||
| 琵琶湖のCODおよびBOD(年平均値)の推移 | |||
|
|||
| 滋賀県「環境白書」より作成 | |||
|
【水質環境基準(COD75%値)の推移】
|
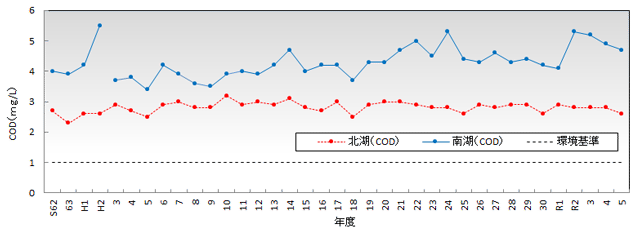 |
|||
| 琵琶湖のCOD(75%値)の推移 | |||
滋賀県「環境白書」より作成
|
|||
|
【水質環境基準(全窒素)の推移】
|
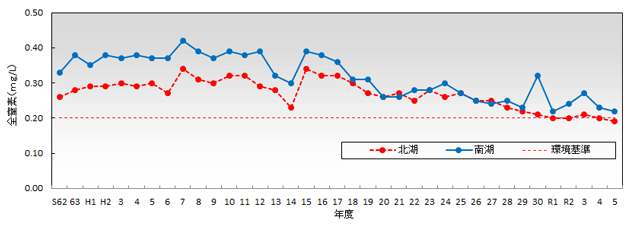 |
|||
| 琵琶湖の全窒素(年平均値)の推移 | |||
滋賀県「環境白書」より作成 |
|||
|
【水質環境基準(全りん)の推移】
|
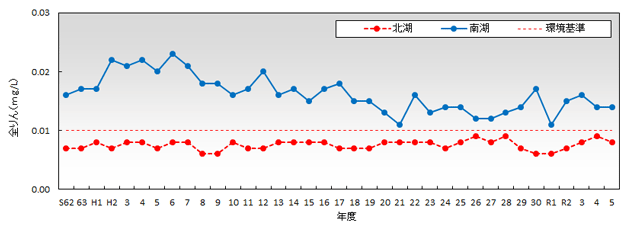 |
|||
| 琵琶湖の全りん(年平均値)の推移 | |||
滋賀県「環境白書」より作成
|
|||
|
【かび臭】
|
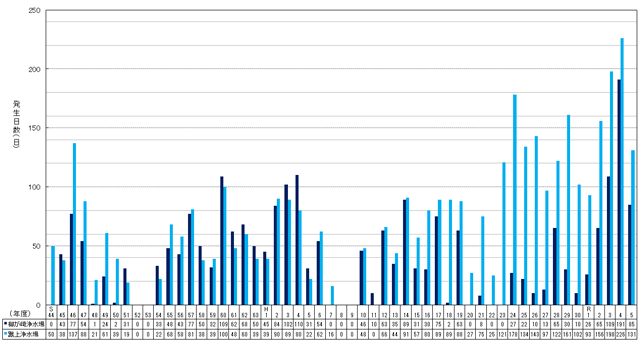 |
||
| かび臭の発生状況 | ||
| 提供:京都市上下水道局技術監理室水質管理センター、大津市企業局水道部水質管理課 | ||
|
【淡水赤潮】
|
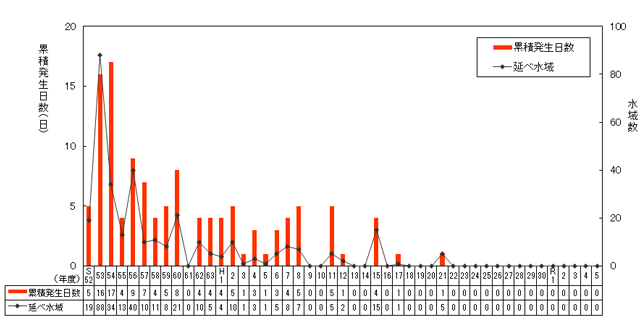 |
|||
| 淡水赤潮の発生状況 | |||
滋賀県「環境白書」より作成
|
|||
|
【アオコ】
|
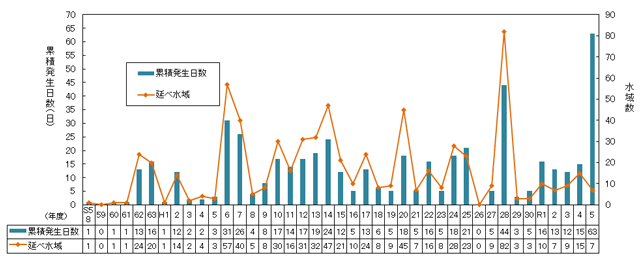 |
|||
| アオコの発生状況 | |||
滋賀県「環境白書」より作成 |
|||